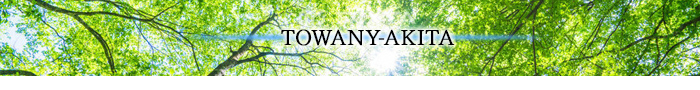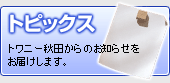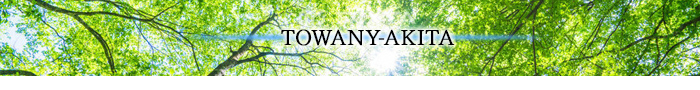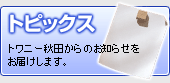|

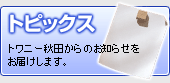

|
 |

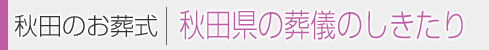
 |
 |
県内外の人の出入りが多いこの時代、最近は各種儀礼式も全国的に平均化の傾向にあります。その一方で古くからの慣習がいまだ根強く残っており、他県の葬式へ弔問に行って戸惑うことや、他県からの親戚の意見に振り回され困惑する御葬家も多くございます。
秋田県内も地域によって様々な特色がありますが、他県との一番の大きな違いは火葬を先に済ませ、葬儀の際にはすでに「お骨」になっていることです。これは「しきたり」ではありませんが、一番大きな特色と言えるでしょう。
「しきたり」にもいろいろありますが、ここではその一例をご紹介します。なお記載されていない地域や、もっと詳細を知りたい事例に関しては、その地域の「トワニー秋田」加盟店にお問い合わせください。
(トワニー秋田加盟店一覧参照) |


 |
■県北地区

 |
| 【1】ご遺体の安置 |
 |
【2】枕飾り~枕経 |
 |
【3】納棺~納棺経 |
 |
| 【4】出棺~火葬 |
 |
【5】通夜(逮夜) |
 |
【6】迎葬~葬式 |
 |
| 【7】埋骨 |
 |
【8】初七日法要(初願忌法要) |
 |
【9】お斎 |
|
 |
| ※ |
近親者、縁者により「枕団子(死に団子ともいう)」や「一本花」を準備し、「死に水」に使用する半紙の「こより」をつくる。 |
| ※ |
町部では寺院での葬式が殆どであるが、農村部では全てを自宅で行う場合が多い。 |
| ※ |
【2】枕経・【4】納棺経・【7】迎葬は寺院により行わない場合もある。 |
| ※ |
納棺はご遺族とともに業者が執行。 |
| ※ |
葬儀より通夜の方が会葬者が多く盛大。 |
| ※ |
友引には火葬をしない(火葬場の休日)。 |
| ※ |
遺族で埋骨を済ませ、その後に和尚様がお勤めする。 |
| ※ |
五、七日(35日)法要まで行う場合が多い。 |
| ※ |
祭壇は通夜から飾り3~4日間、解体後は「後飾り」を使用。 |
| ※ |
寺院での葬儀では寺院備え付けの祭壇を使用する。 |
| ※ |
農村部では「花ふき行列(野辺送り)」をすることも多少ある。 |
|


 |
| 【1】ご遺体の安置 |
 |
【2】枕飾り~枕経 |
 |
【3】納棺 |
 |
【4】出棺~火葬 |
 |
| 【5】お逮夜 |
 |
【6】葬儀~中陰法要 |
 |
【7】忌明法要 |
|
 |
| ※ |
全体的に「友引」を嫌う傾向が強く、死亡の知らせや枕経などもしないこともある。 |
| ※ |
死亡するとすぐ部落や町内中の家々に2人で死亡の知らせをふれまわる地区がある。また、市街地においても死亡通知は2人1組で行うのが一般的である。 |
| ※ |
仏衣は身内の女性達が晒(さらし)を縫って作る場合もある。そのため業者の用意する仏衣も晒製が好まれる。 |
| ※ |
湯灌の儀式には各地区の作法・しきたりが残っているものの、最近では業者が手伝って行う場合が多くなっている。 |
| ※ |
宗派・寺院によって行われない場合があるが、葬儀前夜は近親者が集まりお逮夜が行われる。これは他地域の「通夜」にあたる。 |
| ※ |
葬儀当日に本位牌が必要な寺もある。 |
| ※ |
香典返しは当日返しで、地域によっては香典返しを廃止している所も多い。 |
| ※ |
業者の祭壇は一週間(初七日)で下げ、忌明けまでは各自の“雁木棚”(打敷壇)か、業者の後飾り壇を使用する。 |
| ※ |
忌明けは七、七日(四十九日)。事情により五、七日や三、七日とする場合もある。 |
| ※ |
地域により「葬列」を行う。 |
| ※ |
生花・花環の相場は一墓15,000円~20,000円 |
|


 |
| 【1】ご遺体の安置 |
 |
【2】枕飾り~枕経 |
 |
【3】納棺 |
 |
| 【4】出棺~火葬 |
 |
【5】お逮夜 |
 |
【6】葬儀~初七日法要 |
 |
| 【7】仏送り(8日目) |
 |
【8】35日法要(忌明け) |
|
 |
| ※ |
お逮夜法要は当町の中心部が多い。お寺様から来てもらいお経をあげて法要を営む。葬儀終了後、参加者をおもてなしする。続いて念仏(三十三番御詠歌など)をあげ、こちらも終了後参加者をおもてなしする。 |
| ※ |
葬儀終了後、行列(葬列)をつくり、遺骨を埋葬するため朝8時頃から「ダミ若勢」と称する男性のお手伝いが10名程集まり、葬列に使う葬具を作ったり墓地を清掃したりする。 |
| ※ |
葬列から帰るとお寺様と会食。 |
| ※ |
祭壇は初七日まで飾り、八日目に仏送りを済ませ祭壇を撤去する。 |
|


 |
| 【1】ご遺体の安置 |
 |
【2】枕飾り~枕経 |
 |
【3】納棺 |
 |
| 【4】出棺~火葬 |
 |
【5】お葬儀 |
 |
【6】仏送り~納骨 |
|
 |
| ※ |
ご遺体は北枕にし、屏風で見えないようにする。枕飾りは屏風の前に飾る。 |
| ※ |
枕飾りは枕元に小さな机を置いて白布を掛け、三具足(一本花・香炉・燈明)、四華花、一膳飯、枕団子、水を供える。 |
| ※ |
納棺は業者まかせの場合もあるが、業者立ち会いのもと、身内の人達が行うことが多い。 |
| ※ |
香典返しは葬式の日に「当日返し」。また、地域のよっては「お悔やみ」に来られたときに香典返しをする所もある。 |
| ※ |
地域で祭壇を準備している所もある。 |
| ※ |
納骨は葬式の当日が殆どである。 |
| ※ |
初七日の翌日に祭壇を撤去。但し、一向宗で一部、葬儀翌日に祭壇を撤去する所もある。 |
| ※ |
生花・花環・タオル花環・缶詰 等の平均価格は、一基20,000円。 |
|
|
 |
 |
 |
■中央地区

 |
| 【1】ご遺体の安置 |
 |
【2】枕飾り~枕経 |
 |
【3】納棺 |
 |
| 【4】出棺~火葬 |
 |
【5】お逮夜 |
 |
【6】葬儀~中陰法要 |
 |
【7】忌明法要 |
|
 |
| ※ |
納棺は夕方行う。最近は主に業者が行うが、少々は身内の人が行うことがある。 |
| ※ |
火葬は「友引」関係なくできる。 |
| ※ |
生花の相場は20,000円より。花輪は10,000円より。 |
|


 |
| 【1】ご遺体の安置 |
 |
【2】枕飾り~枕経 |
 |
【3】納棺 |
 |
| 【4】出棺~火葬 |
 |
【5】お通夜 |
 |
【6】葬儀~中陰法要 |
 |
| 【7】納棺 |
 |
【8】中陰法要 |
 |
【9】忌明法要 |
|
 |
| ※ |
町部では寺院での葬式が多く、農村部では自宅での葬式が多い。また町部では「通夜」があり、葬儀より会葬者が多い。 |
| ※ |
地区によっては「通夜」が無く、葬儀当日の朝香典を持って会葬にくる所もある。 |
| ※ |
祭壇は初七日、もしくは次の日位で撤去する。 |
| ※ |
一部の地区を除いて友引きでも火葬をする。 |
|
|
 |
 |
 |
■県南地区
| 雄物川町・大森町・大雄村・平鹿町・十文字町・羽後町・東由利町方面 |

 |
| 【1】ご遺体の安置 |
 |
【2】枕飾り~枕経 |
 |
【3】納棺 |
 |
| 【4】出棺~火葬 |
 |
【5】葬儀~35日法要 |
 |
【6】仏送り |
|
 |
| ※ |
通夜は殆ど無い。 |
| ※ |
納棺は業者まかせの場合もあるが、殆どは業者と一緒に身内の人が行う事が多い。 |
| ※ |
丑の日を避けることが多い。 |
| ※ |
会葬者は葬式よりも、自宅に「仏さん拝み」と言って訪れることが多く、
酒食を頂いていく。
3週間祭壇を飾るため、その間の炊事の負担が大きい。 |
| ※ |
葬式は自宅が8割、お寺が2割。 |
| ※ |
生花・花環の相場は一基15,000円~20,000円 |
|


 |
| 【1】ご遺体の安置 |
 |
【2】枕飾り~枕経 |
 |
【3】納棺 |
 |
| 【4】出棺~火葬 |
 |
【5】葬儀~35日法要 |
 |
【6】仏送り |
|
 |
| ※ |
身内が集まっての「通夜」はあるが、“儀式”としての「通夜」はなく、お寺も「通夜経」をあげに来ない。 |
| ※ |
納棺は業者まかせの場合もあるが、殆どは業者と一緒に身内の人が行う事が多い。 |
| ※ |
一部に地域で「丑の日」「寅の日」を避ける所もある。 |
| ※ |
香典返しは当日返し(葬式の日)だが、火葬場近隣の地域では火葬場にも
一般会葬者が来るため、火葬場でも「お返し」を用意することが多い。 |
| ※ |
地域によっては香典返し廃止の取り決めをしている所もある。 |
| ※ |
家が狭い等、特別な事情がある場合を除いて、自宅の祭壇は仏送りが終わるまで飾る(一般的に3週間)。 |
| ※ |
生花・花環の相場は一般的に15,000円前後。一対ではなく1基であげる。 |
|
|
|