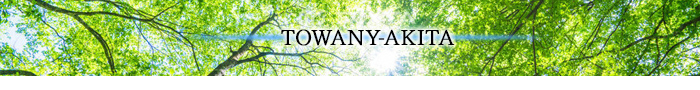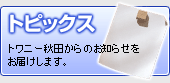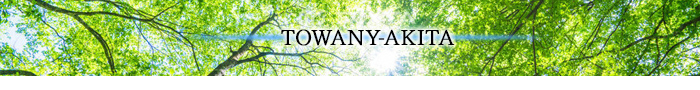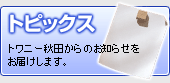|
| ●香典返しは忌明けに |
| 一般には仏式で忌明け法要後に満中陰のあいさつに添えて、香典返しの品を届けます。神式なら五十日祭の後に、キリスト教では一・二週間または一ヵ月後の昇天記念日の後が多いようです。多少おくれてもよく、早くなることは避けた方が良いとされています。 |
 |
 |
| ●お位牌・仏具等の購入は忌明けまでに |
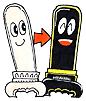 |
| 葬儀までの位牌や法名は仮のものです。忌明けまでに本位牌や法名軸に戒名・法名を移します。また、葬儀が終わっても法事等で仏具が必要です。葬儀社等でもお貸ししますが、足りないものは買いそろえましょう。仏壇のない家庭では小机に遺骨・遺影・位牌を安置し、新しい仏壇に納めると良いでしょう。 |
 |
 |
| ●形見の品は包装しない |
| 近親者や特に親交の厚かった方へ、故人の愛用の品々を分けますが、かえって迷惑ということのないよう慎重に選びましょう。この際包装やのしをかけることはしないで形見の品を裸のまま渡すのがしきたりです。 |
 |
 |
| ●初七日・忌明けはていねいに |
| 仏式では、葬儀の後の法要は、死去した日を基準に、忌明けまで七日ごとにします。特に初七日・忌明けを大切にし、僧侶に読経を頼んでその後、近親者・親しい友人に茶菓や料理をもてなして、故人の冥福を祈ります。 |
 |
 |
| ●法要の案内状出欠の返事をもらう |
 |
| 一周忌まではやや大がかりでも、三回忌ごろから内輪の集まりになることが多いようです。法要の案内は電話でも差しつかえありませんが、案内状の場合は出欠の返事をもらえる様返信用ハガキを添えると、準備上便利。大がかりな場合は、印刷を頼むと見本もあり失敗がありません。 |
 |
 |
| ●遺品の整理は早めに |
| 特に、故人が働いていた場合、職場の遺品の整理はできるだけ早く行いたいものです。同時に、同僚やいきつけの店に借用金品等がないかを確認し、きちんと処理します。また、家庭の遺品も早めに整理分類を。 |
 |
 |
| ●僧侶への謝礼はその時々で |
| 正式な法要では、御布施料または御経料の他御車代、接待をしない場合の御膳料が必要となります。けれども、内輪の法要であれば、御布施としてひとつにまとめてお渡ししても良いでしょう。 |
 |
 |
| ●中元・歳暮は紅白の水引なしで |
| 四十九日後ならば、お中元・お歳暮の贈答は差し支えありません。ただし、いずれも、紅白の水引を使うことは避けるのが、礼にかなった方法です。 |
 |
 |
| ●12月の初めに年賀欠礼の知らせを |
 |
| 喪中には年賀状は出しません。そこで12月の初めに、「喪中につき年頭のごあいさつをご遠慮申し上げます」等のハガキを送ります。喪中欠礼の通知をしないと、新年早々に喪中を知らせる結果となり、失礼にあたります。 |
 |
 |
|